
|
共通認識として持てることが、環境を守ることになると考えられます。そういう意味で、地域活動は重要です。
下の表は、自然観察会の実施内容を月別に記したものです。生徒の興味と関心を引きつけ、季節にあったテーマで実施しました。
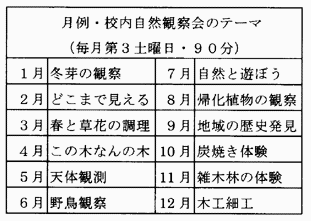
これらの内、4つの内容について次のように解説を加えました。小中高を問わずに実施してみて下さい。
2 自然と過ごす小さな遊び(7月)
校庭で見られる身近な自然といえば、空地に生える草花や記念樹として植栽された樹木などです。その樹木には多くの野鳥が木の実や虫を求めて集まり、ときに営巣することもあります。自然を理解するには、積極的に遊びを取り入れ、より具体的に自然と接することだと思います。季節に応じた校内自然観察会を実施することは、自然の変化や動植物の営みを理解することになります。そして、その体験が自然を守っていくことにつながります。自然に親しみ、自然を理解し、自然を守っていく心を育てましょう。
つぎのような内容の活動シートを作成し、実行してみました。
[さあ、自然視察ビンゴをはじめましょう!]
校庭を散策しながら、身近な植物や野鳥・昆虫などに触れて、その特色をじっくり観察します。そのあとに質問を出します。質問は全部で9題です。答えは下のカードに記入します。全問正解の生徒やビンゴ賞には、記念品(枝で作った鉛筆やブローチなど)をプレゼントします。
[自然観察ビンゴカード]
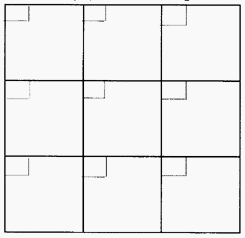
?@左上の小さいマスに1〜9の番号を適当に入れて下さい。
?Aこれから歩く中で、9つの質問をします。正解であれば、数字の部分に[○]印をし、縦・横・斜めが3つそろったら「ビンゴ」と大きな声で叫びます。
?B五感を活用して、自然をしっかり観察しましょう。
それでは、校内不思議発見の観察に出かけましょう。(実際に行った9の質問とその解説を次に紹介します。)実際のシートでは質問だけを印刷しました。
問1 植物の葉に隠された不思議な記号
ヒノキの葉裏に不思議な記号が描かれています。その記号(アルファベット)を調べてカードに書きましょう。
ヒノキの葉裏には、白い気孔線が見られます。アルファベットの[Y]が連続しているように見えます。
(サワラ:[X]アスナロ:[W])
前ページ 目次へ 次ページ
|

|